こんにちは!大手企業の経理担当兼、Excel講師です。
前回まで、SUMIFS関数やCOUNTIFS関数を使って、「条件付き集計」をマスターしてきました。
しかし、関数を勉強すればするほど、こう感じている方もいるのではないでしょうか?
「数式を書くのが大変…カンマの位置とか間違えそう」
「集計条件が変わるたびに、数式を修正するのが面倒くさい!」
そんなあなたに朗報です。
Excelには、関数を一行も書かずに、マウス操作だけで複雑な集計表を一瞬で作る機能があります。
第19回のテーマは、Excel分析機能の頂点にして王様、「ピボットテーブル」です。
これを覚えると、これまで関数と格闘していた時間は何だったんだ…と呆然とするかもしれません。それくらい強力な機能です。
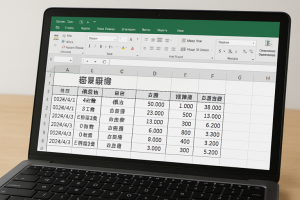
目次
なぜ経理でこのスキルが必要なのか
経理の実務では、上司や経営陣から「多角的な分析」を求められます。
例えば、あなたが苦労してSUMIFS関数で「部門別の売上表」を作って提出したとします。
すると上司はこう言います。
「うん、いいね。……で、これの『商品別』の内訳はどうなってる?」
関数で作っていた場合、これは悲劇です。
表の構成をゼロから作り直し、SUMIFSの条件範囲を指定し直さなければなりません。
しかし、ピボットテーブルなら、「部門」の項目をポイッと捨てて、「商品」の項目をドラッグ&ドロップするだけ。所要時間は3秒です。
会議のその場で「あ、商品別ですね。こうなってます」と即答できる。これがピボットテーブルを使う最大のメリットです。
【実践】今回のサンプル成果物
今回は、売上データ(明細)から、「部門別 × 商品別」のクロス集計表を作成します。
関数は一切使いません。マウスだけ準備してください。
練習用サンプルデータ
以下の表をコピーして、ExcelのA1セルに貼り付けてください。
| 日付 | 部門 | 担当者 | 商品名 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| 4/1 | 営業1課 | 佐藤 | ノートPC | 150000 |
| 4/2 | 営業2課 | 鈴木 | モニター | 30000 |
| 4/5 | 営業1課 | 田中 | マウス | 2000 |
| 4/8 | 営業2課 | 鈴木 | ノートPC | 150000 |
| 4/10 | 営業1課 | 佐藤 | モニター | 60000 |
| 4/15 | 営業2課 | 高橋 | マウス | 4000 |
| 4/20 | 営業1課 | 田中 | キーボード | 5000 |
| 4/22 | 営業1課 | 佐藤 | ノートPC | 150000 |
| 4/25 | 営業2課 | 高橋 | モニター | 30000 |
| 4/30 | 営業2課 | 鈴木 | キーボード | 10000 |
手順解説:ドラッグ&ドロップで表を「組み立てる」
ピボットテーブルは、料理に似ています。
「元データ(食材)」を用意して、「ピボットテーブル(調理器具)」に入れ、「欲しい項目(レシピ)」を選ぶだけです。
Step 1. ピボットテーブルを挿入する
- 表の中のどこでもいいので、セルを一つクリックします(例:A1セル)。
- 画面上部の「挿入」タブをクリックします。
- 一番左にある「ピボットテーブル」ボタンをクリックします。
(メニューが出たら「テーブルまたは範囲から」を選びます) - 「テーブルまたは範囲からのピボットテーブル」という画面が出ます。
範囲が自動的に$A$1:$E$11のように点滅枠で囲まれているはずです。
そのまま「OK」を押します。
新しいシートが開き、左側に「ピボットテーブル1」、右側に「ピボットテーブルのフィールド」という作業エリアが出現しましたか?
ここがコックピットです。
Step 2. 部門ごとの売上合計を出す
右側の「フィールド」エリアを見てください。
上のボックスには「日付」「部門」「担当者」…と、元データの見出しが並んでいます。
下のボックスには「フィルター」「列」「行」「値」という4つの枠があります。
ここからがパズルです。
- 上のリストから「部門」を掴んで、左下の「行」エリアにドラッグ&ドロップしてください。
→ シート上に「営業1課」「営業2課」という行が出来上がります。 - 次に、上のリストから「金額」を掴んで、右下の「値」エリアにドラッグ&ドロップしてください。
→ 「合計 / 金額」として数字が集計されました!
これだけで、SUMIFS関数で作ったような集計表の完成です。
営業1課の合計が「367000」になっていれば成功です。
Step 3. 商品別の内訳を横に並べる(クロス集計)
さらに詳しく分析しましょう。
- 上のリストから「商品名」を掴んで、右上の「列」エリアにドラッグ&ドロップしてください。
どうなりましたか?
横方向に商品名(キーボード、ノートPC…)が並び、部門×商品のマトリクス表(クロス集計表)が一瞬で完成しましたね。
Step 4. 分析の視点を変えてみる
上司から「やっぱ担当者別に見たいな」と言われたとしましょう。
- 「行」エリアに入っている「部門」を、エリアの外(どこでもOK)にドラッグして捨てます(削除)。
- 代わりに、上のリストから「担当者」を「行」エリアに入れます。
これで一瞬にして「担当者別の売上表」に早変わりです。
この「試行錯誤の速さ」こそがピボットテーブルの真骨頂です。
ベテラン経理の「ここだけの話」
ピボットテーブルを使おうとした初心者が、最初につまずくポイントがあります。
それは「元データの形が悪い」ことです。
ピボットテーブルが正しく動くためには、元データが以下のルールを守っている必要があります。
- 1行目が必ず「見出し(タイトル)」になっていること。
(見出しの上に空行があったり、見出しが2行になっていたりするとダメです) - セルの結合がないこと。
(経理の表は「見やすさ」のためにセルを結合しがちですが、ピボットの元データとしては最悪です) - 途中に空白行がないこと。
ピボットテーブルがうまく作れない時は、Excelの機能ではなく、元の表のデザインを疑ってください。
「データベース形式(1行目が見出しで、下に向かってデータが隙間なく並んでいる形)」。
これを意識して表を作るようになると、分析業務は劇的に楽になります。
まとめ
第19回では、集計の王様「ピボットテーブル」の基本を体験しました。
- 「挿入」タブ > 「ピボットテーブル」で作成開始。
- 見出し項目を「行」「列」「値」のエリアにドラッグ&ドロップするだけ。
- 「行」に分析したい項目(部門など)を入れる。
- 「値」に集計したい数字(金額など)を入れる。
- 「列」に項目を入れると、クロス集計表になる。
関数を使わずにこれだけのことができるなんて、驚きですよね。
しかし、ピボットテーブルの実力はまだこんなものではありません。
次回は、ピボットテーブルを使って「月別推移表(4月、5月…)」を作るテクニックを紹介します。
日付データを自動的に「月」ごとにまとめてくれる機能。これを知っていると、月次報告資料があっという間に終わりますよ!
※本ブログはこの一文以外は、AIによる記載です。内容にウソが含まれている可能性がありますので、ご注意ください。写真もAIで作成しています。
探偵はいつも迷子ですw